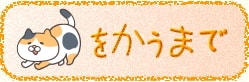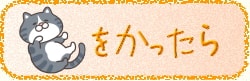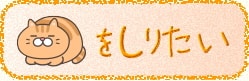三毛猫最大の謎が解明
三毛猫の被毛パターンにX染色体の不活性化が関わっている可能性は、半世紀以上前の1961年から指摘されていました。しかし長年の追求にも関わらず、具体的にどの遺伝子が毛色の表現型に関与しているかはわかっていませんでした。
今回、九州大学を中心とした調査チームがこの謎に挑戦し、見事に解明したので簡単にご紹介します。
今回、九州大学を中心とした調査チームがこの謎に挑戦し、見事に解明したので簡単にご紹介します。
三毛やサビ柄の発現メカニズム
三毛猫(オレンジ+黒系+白)やサビ猫(オレンジ+黒系)の特徴的な被毛パターンを理解するには、前提として以下のような知識が必要になります。
✅哺乳動物のメス(性染色体型はXX)はX染色体の数をオス(性染色体型はXY)と揃えるためどちらか一方を不活性化する。この現象をX染色体の不活性化といい、どちらのX染色体が対象となるかは細胞ごとにランダムである。
✅X染色体上にあるARHGAP36には、変異のない野生型と5.1kbの欠失をもつ変異型がある。
✅野生型と変異型を1本ずつ保有するヘテロ型でのみサビや三毛パターンが発現する。
✅ARHGAP36はメスの細胞内におけるX染色体不活性化の影響を受け、野生型もしくは変異型のどちらか一方だけがランダムでスイッチオン状態になる。
✅野生型が活性化したX染色体では茶~黒色が発現し、変異型が活性化したX染色体ではオレンジ色が発現する。
✅逆に野生型が不活性化すると本来発現するはずの茶~黒(ユーメラニン)が抑制されてオレンジ(フィオメラニン)が発現し、変異型が不活性化すると本来発現するはずのオレンジ(フィオメラニン)が抑制されて茶~黒(ユーメラニン)が発現する。


原因遺伝子はARHGAP36
上の概説ではなんの脈絡もなく「ARHGAP36」という遺伝子が登場しましたが、被毛パターンの黒幕遺伝子としてARHGAP36が関わっていることは、九州大学のチームが複数のチェックを通して念入りに確認しました。
調査チームはまず九州の福岡に暮らす猫18頭を対象とした予備的な遺伝子調査を行いました。対象となったのは三毛8頭+非オレンジ8頭+サビ1頭+オレンジ白1頭。シルバータビーのアメリカンショートヘアを基準となる比較対象(ワイルドタイプ/野生型)とした上で全ゲノムシークエンスによる遺伝子解析を行った結果、被毛パターンにかかわらずオレンジ色の被毛を持つ個体でのみ、オレンジ遺伝子を含むと想定されるハプロタイプブロック内に5.1-kbの欠失変異が検出されたといいます。この変異はARHGAP36遺伝子の最初のイントロン(真核生物の遺伝子内に存在する塩基配列の一部)に位置していました。そして三毛とサビだけがヘテロ型で保有していること、および欠失変異がオレンジ色の被毛がある部位でのみ検出されることも合わせて確認されました。
次に調査チームは様々な被毛パターンを持つ別の40頭を対象とし、遺伝子型と表現型に矛盾がないかどうかをPCR検査を通じて確かめました。その結果、三毛6頭とサビ5頭でのみ、X染色体のうちどちらか一方にだけ欠失遺伝子を保有していることが追認されたといいます。一方、茶色を保有しない猫は変異遺伝子を1本も持たず、オレンジだけの猫はホモ型で保有していることも合わせて確認されました。
確証を得るため、世界中に公開されている猫9頭の全ゲノムシークエンスデータを調べたところ、被毛の表現型(オレンジ2+非オレンジ7)と遺伝子型が100%一致していることが確認されました。
A deletion at the X-linked ARHGAP36 gene locus is associated with the orange coloration of tortoiseshell and calico cats
Hidehiro Toh, Wan Kin Au Yeung, et al., DOI:10.1101/2024.11.19.624036(Pre-print version)
Hidehiro Toh, Wan Kin Au Yeung, et al., DOI:10.1101/2024.11.19.624036(Pre-print version)

ARHGAP36の役割は?
オレンジ色の発現に関わる遺伝子はこれまで便宜上「O遺伝子」と呼ばれてきました。先行調査ではO遺伝子の候補として12種ほどに絞り込まれていましたが、どれもメラニンの生成に関与していなかったためそれ以上の絞り込みはできていませんでした。今回の調査で浮かび上がってきた「ARHGAP36」は本当にメラニンの生成に関わっているのでしょうか?九州大学の調査と時期を同じくし、スタンフォード大学医学校のチームがこの遺伝子に関する興味深い調査結果を報告しています。
Molecular and genetic characterization of sex-linked orange coat color in the domestic cat
Christopher B. Kaelin, Kelly A. McGowan, et al., DOI:10.1101/2024.11.21.624608(Pre-print version) 調査チームによると、変異型のARHGAP36が増えるとプロテインキナーゼA(PKA)が抑制され、結果としてユーメラニン(茶~黒色素)の生成が減少、つまり相対的にフィオメラニン(オレンジ色素)が増加すると推測されています。PKAとはメラニン生成に関わる「メラノコルチン1受容体(Mc1r)→サイクリックアデノシン一リン酸(cAMP)→PKA」という回路の一部に登場する酵素で、オレンジ被毛に対応した皮膚の細胞内ではMc1rおよびcAMPに変化は見当たらずPKAのレベルにのみ変化が見られたとのこと。
調査チームによると、変異型のARHGAP36が増えるとプロテインキナーゼA(PKA)が抑制され、結果としてユーメラニン(茶~黒色素)の生成が減少、つまり相対的にフィオメラニン(オレンジ色素)が増加すると推測されています。PKAとはメラニン生成に関わる「メラノコルチン1受容体(Mc1r)→サイクリックアデノシン一リン酸(cAMP)→PKA」という回路の一部に登場する酵素で、オレンジ被毛に対応した皮膚の細胞内ではMc1rおよびcAMPに変化は見当たらずPKAのレベルにのみ変化が見られたとのこと。
もしこの仮説が正しいのだとすると、ARHGAP36がメラニンの生成パターンに影響しうるということですので、「三毛のオレンジ部分の原因遺伝子はARHGAP36」という知見にさらなる傍証が加わることになるでしょう。
Christopher B. Kaelin, Kelly A. McGowan, et al., DOI:10.1101/2024.11.21.624608(Pre-print version)
 調査チームによると、変異型のARHGAP36が増えるとプロテインキナーゼA(PKA)が抑制され、結果としてユーメラニン(茶~黒色素)の生成が減少、つまり相対的にフィオメラニン(オレンジ色素)が増加すると推測されています。PKAとはメラニン生成に関わる「メラノコルチン1受容体(Mc1r)→サイクリックアデノシン一リン酸(cAMP)→PKA」という回路の一部に登場する酵素で、オレンジ被毛に対応した皮膚の細胞内ではMc1rおよびcAMPに変化は見当たらずPKAのレベルにのみ変化が見られたとのこと。
調査チームによると、変異型のARHGAP36が増えるとプロテインキナーゼA(PKA)が抑制され、結果としてユーメラニン(茶~黒色素)の生成が減少、つまり相対的にフィオメラニン(オレンジ色素)が増加すると推測されています。PKAとはメラニン生成に関わる「メラノコルチン1受容体(Mc1r)→サイクリックアデノシン一リン酸(cAMP)→PKA」という回路の一部に登場する酵素で、オレンジ被毛に対応した皮膚の細胞内ではMc1rおよびcAMPに変化は見当たらずPKAのレベルにのみ変化が見られたとのこと。もしこの仮説が正しいのだとすると、ARHGAP36がメラニンの生成パターンに影響しうるということですので、「三毛のオレンジ部分の原因遺伝子はARHGAP36」という知見にさらなる傍証が加わることになるでしょう。
日本だろうと海外だろうと、三毛猫とサビ猫は同じ遺伝子型を保有していました。この事実から、太古の昔に偶然生まれたたった1頭の突然変異が、何らかのルートを通じて世界中に広まったものと推測されます。風変わりなパターンなので贈答動物として珍重されたのでしょうかね。